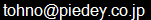|
||||||
|
Q氏は頭を抱えていた。 理由は、会社から課せられた特許のノルマだった。 会社が数多くの特許が必要とする理由の第1は、もちろんそれが収益を産むからだが、それだけではない。他社が自社製品に対して特許を持ち出してクレームを付けてきたとき、こちらも相手会社製品に対して何かをしうる特許があれば相殺できるからだ。つまり、自社製品を防衛する手段になる。だから、あらゆる種類のあらゆる特許をともかく得ておく価値がある。自社の業務内容と関係ない特許も網羅的に得ておく必要がある。 しかも、申請されているのに存在が公表されないサブマリン特許というやっかいな代物があるので、十分な事前調査だけでは対処できず、どうしても保険的に多数の特許を持つ必要があったのだ。 というわけで、社員に特許のノルマが課せられるわけだが、そうそう都合良く新しいアイデアが出てくるわけがない。 異能のサラリーマンとして持てはやされたQ氏にしても、そうそう都合良く定期的にアイデアが浮かぶわけではない。 そのような訳で、Q氏は昨日からずっと思い浮かばない特許について悩んでいたのである。 しかし、さすがは異能のサラリーマン。人知を尽くしてダメなら神頼みしかないとすぐ気付き、油揚げを持って近くのお稲荷さんに行った。 特上の油揚げを持って行ったおかげか、その夜、夢枕に年老いたキツネが現れた。 「おまえの望みを言え。可能なことなら叶えてやろう」 「特許が欲しいのです。何でも良いから特許が欲しいのです」 「ふむ。特許を1つということかな?」 「いえ、ノルマは定期的に課せられます。順調にサラリーマン生活を定年まで勤めるなら、百個は。いや、会社から期待されてノルマを増やされてきた実績からすれば、千個はないと足りません」 「ふむ。既におまえはいくつもの特許を思い付いたというのだな?」 「その通りです」 「ならば、新しい特許のアイデアを授けるよりも、1つのアイデアを千倍に増やす術を授けた方が良さそうじゃのう」 「千倍! そんなことができるのですか!!」 「わしを誰だと思っておる。キツネの神様であるぞ。コーン!」 翌朝、目覚めたQ氏の頭の中には画期的な「特許千倍の術」が残っていた。 どういう理屈かは分からないが、呪文を唱えながら用紙に向かうと、いくつでも特許を書けるのだ。 Q氏は猛烈に特許を書き続け、ついに千個の特許を書き上げた。そこで術の力は効力を失った。 だが、Q氏は考えた。この術は元になる特許を千倍にする術だ。ならば、術で作った特許を元にしてもう一度術を使えば、千個の特許それぞれが千個の特許を産み、百万個の特許になるのではないか? Q氏は即座にそれを試し、推理が正しかったことを確認した。ねずみ算式にいくらでも特許が作れる! Q氏はひたすら百万個の特許を書き続けた。 会社はQ氏を称え莫大なボーナスを支払った。社会は、Q氏をヒーローとして称えた。そして、東京特許許可局は、処理能力を超えたQ氏からの特許申請に悲鳴を上げた。 Q氏はまさに得意絶頂だった。 そのQ氏に1人の男が訪れた。 その男は告げた。 「あなたの特許千倍の術の使い方は、我が社の所有する特許を侵害しております」 「そんなバカな。特許千倍の術はキツネの神様から直々に教わったものだ」 「特許千倍の術は神界において公知の技術ですから、特許にはなりません。我々が持っているの特許は、特許千倍の術で作られた特許に対して再度特許千倍の術を用いることで、ネズミ算式に特許を増やす方法です」 「まさか!」 「というわけで、最初に特許千倍の術で作られた特許については何も言いません。その後、特許千倍の術で作った特許に再度特許千倍の術を用いて作った百万個の特許について、使用料を頂きます」 「まさか。会社からもらった莫大なボーナスがそれで消えてしまうというのか?」 「いえ。その程度の金額では到底収まりません。なにせ、百万個ですから。そうですね。金額は、あなたがもらったボーナスの千倍ぐらいになるでしょうか」 Q氏はその場でひっくり返った。 (遠野秋彦・作 ©2008 TOHNO, Akihiko) |
|
||
|
|